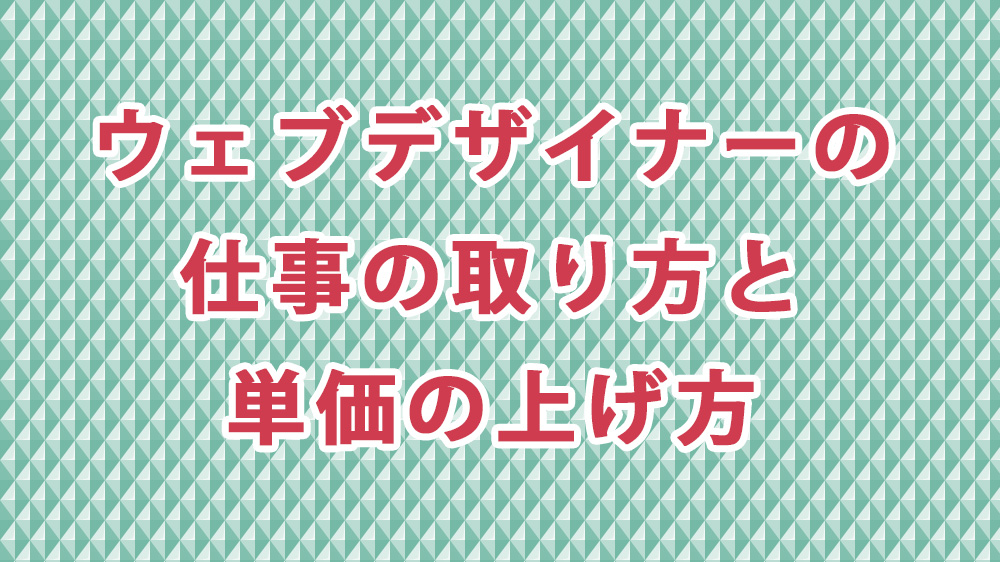
こんにちは。こんぶだし茶です。
この記事は、これからWEBデザイナー(ウェブデザイナー)のフリーランスとして活躍したい人に、仕事の取り方についてお話しします。
ウェブデザイン会社で働いたことがない人にも役に立つとおもいます。
ぼくは、17年関フリーランスをして、ウェブデザインも開発も両方経験しました。
ついでながら、新人社員研修や、デザイナー学校、プログラミングスクール等で教えたこともあります。
フリーランスをやっていくことは、デザイン会社での経験があっても、なくても、高いハードルです。
難しいといっても、僕は文字通り七転八倒しながら仕事を獲得していったわけですが、
もうちょっとスマートなやり方があるので、その点をお伝えしたいと思います。
では、これから同業・生徒等さまざまな人の経験を通して得られた、フリーランスが仕事を得る方法をお伝えします。
どうやって仕事を取る?
まず初級編です。この辺の情報はどこのブログにも載っているかもしれませんが、おさらいしておきましょう。
仕事を取るにはポートフォリオを作って、仕事を求めて営業するという流れが基本です。
まずポートフォリオを作る
仕事を取るために、まずはポートフォリオを準備します。
ポートフォリオというのは、これまでの作品の履歴です。
ウェブデザイナーであれば、ポートフォリオサイトを作って公開するのが一般的です。
ポートフォリオは自分のアピールをするための宣伝材料であり、主に4つのことを伝えます。
ポイント
(1)過去に何件の発注を受け、何件の作品を作った経験があるか
(2)デザインの幅、得意ジャンル
(3)技術力。特にモダンな開発に対応しているか
(4)作品ごとの制作期間(時間)
(1)過去に何件の発注を受け、何件の作品を作った経験があるか
これについては、実績がどれくらいあるかを証明するものです。
経験は簡単に作れます。まず、親・親戚で事業者がいれば、そのウェブサイト制作、リニューアルを申し出てみます。
心当たりがない場合は、知人を探します。
私は過去にうちの近所にある美容室のウェブサイトを作らせてもらいました。
自分が推している地下アイドルの公式ウェブサイトを作った人もいます。
ウェブサイトを必要としている人はたくさんいますので、経験を積むのは簡単です。
(2)デザインの幅、得意ジャンル
この点については、あまり触れる人がいませんが、
デザインのテイストについて、得意分野が1つに偏らないようにすることが大事です。
ウェブデザイナーの仕事は忙しく、終始営業をしているわけにはいきません。
そのため、デビュー後の最初の目標は、
仕事を繰り返し発注してくれる、気の合う人を2、3人つかまえることになります。
そういった繰り返し発注する側の人にとって、
「かわいいのしか作れない人」
「男っぽいものしか作れないもの」
といったように、一つのテイストしか出せない人は、何度もお願いしづらいのです。
もちろん、最初からすべてのことが出来る人なんていませんが、
仕事が途切れない人になるためには、ぜひ、複数のテイストが作成できるデザイナーを目指してください。
(3)技術力。特にモダンな開発スタイルに対応しているか
ウェブデザインの仕事も細分化されていて、他人が作成したデザインを再現する仕事の人もいます。
一般的に「コーダー」と言われます。
「コーダー」の人は特に技術力が問われます。
デザインスクールに行っている方が多いと思いますが、それだけでは知識利用は不足します。
その部分はブログで勉強したり、勉強会に参加したり積極的に吸収します。
もっとも、この点は、どのウェブデザイナーも意識が高いかもしれませんね。
(4)作品ごとの制作期間(時間)
ウェブデザインの仕事は、締め切りとの戦いです。
いくら綺麗なものが作れる技術力・デザイン力をもっていたとしても、作るのが遅い人には頼めません。
ポートフォリオの作品は、「どれくらいの時間をかけて作ったか」と聞かれます。
即答で答えられるようにしておきたいところです。
そのため、デビュー前から、常に時間を図って作品を作ることをお勧めします。
仕事を求めて営業する
ポートフォリオサイトを用意したら、営業を行います。営業先はいくつもあります。
エージェントに営業する
レバテックフリーランスといったエージェントは、仕事を依頼したい企業と、仕事の依頼を受けたいフリーランスの橋渡しをします。
エントリーし、エージェントとお会いするかオンラインのミーティングを行います。
登録自体は難しくないので、最初に登録しておくことをお勧めします。
また、最初のポートフォリオの内容が充実していないせいで、仕事を貰えなかったとしても、
経験を積みながら、ポートフォリオを充実させ、定期的にポートフォリオについてエージェントに連絡することで、
仕事の発注を受けられるようになります。
クラウドソーシングで仕事を探す
クラウドワークスなどのクラウドソーシングは、仕事をしてほしい人と仕事をしたい人をマッチングするサービスです。

![]()
また、フリーランス初心者にとって取り組みやすい、小さなご依頼もたくさん見つかります。
ただし、クラウドソーシングだけでなく、クラウドソーシング全体について言えることですが、
他の方法でとる仕事よりも安価です。
また、発注する側も「長く良好な関係を作りたい」と考える人よりも
「とにかく安く、早く、ある程度のクオリティのものが欲しい」という人が多いです。
お互いに一回限りの、ドライで割り切ったビジネスとなることを覚悟していれば、
利用しやすいサービスであると思います。
発注する側の人と、直接対面してお話しする機会はあまりなく、ほとんどが、クラウドソーシング内の
メッセージのやり取りで完結するので、「最初から相手と話しながら仕事を進めるのは緊張する」という方にも向いていると思います。
同業者・知人から仕事を得る
私はこの方法をお勧めしますが、知り合いから仕事を貰うことです。
今、ウェブデザインスクールに在籍している場合は、チャンス。
将来仕事がもらえるかもしれませんので、積極的にSNS等でつながりましょう。
僕の最初の仕事は、僕がスクールに通っていたときに同じスクールの友達から紹介されました。
その後現在になっても、仕事を紹介してもらっています。
ぜひ、学校の行事などめんどくさがらずに参加して、いろんな人とつながりを持っておいてください。
スクールに行っていなくても、ウェブの勉強会はたくさん行われています。
小さいことでいいので、発表者側にまわって、覚えてもらうようにしましょう。
そういう経験を2、3度していると、本を書いたりしている有名ウェブデザイナーとも簡単に知り合えます。
発表する機会をもちつつ、仕事を募集しているということを明確に伝えると、仕事を請ける機会はすぐに飛び込んできます。
広告を出稿する
絶対に仕事をこなせる自信があるのであれば、グーグル広告などで広告を出稿して、仕事を請けます。

広告を出すにしても「ウェブデザイナーです。仕事募集してます」という広告だと誰にも刺さらないので、
専門的なウェブサイトを提供する必要があります。
たとえば、ですが(この例のとおりやっても、既に競合がいて難しいかもしれませんが)
「今年司法書士で開業した方、ウェブサイトにお困りではありませんか」
「5年放置したホームページはもう時代遅れ。リニューアルで購入しやすく改善」
「生鮮食品専門のECサイト構築支援します」
といった広告を出し、問い合わせから発注へとつなげるのです。
もちろん、仕事の発注を受けるより先に広告費を支出し続けるので、怖い面もありますが、
「60,000 円をお使いいただくと、60,000 円の無料広告クレジットが提供されます。」(終了する可能性があります)
とあるので、6万円を使えるのなら、12万円でどれくらい問い合わせがあり、どれくらい発注を受けるのか試すことが出来ます。
上手くはまれば、自動集客し続けて毎月の仕事と売り上げを獲得することが可能です。
とはいえ、この方法は商才も必要となるため、自己責任でやれる勇気があるかたのみ挑戦してください。
SNSでPRすることで仕事を得る
最後のこの方法は、僕はやったことがないので簡単に紹介します。
これは、SNSで関係を作りつつ、何度かいいね、コメントしお互いが認知される関係になったところに
DMで仕事の提携をしませんかと申し出る方法です。
もっと上手なSNSの活用方法があるかもしれません。
それから、LinkedInはビジネスのつながりを作るのを前提としたつながりですので、LinkedInを活用するほうが、
仕事をくださいというPRをしやすいと思います。
営業で大事なこと:自信がないことは載せない、言わない
ポートフォリオを誰か他の人に見せるときに、うっかりやってしまっているのが
「いいわけ」です。
たとえば、「これはちょっと出来が良くなかったかなと思っていて」とか、
「これは実は最終的には仕事になってなくて」とかいうものです。
フリーランスになるのであれば、あらかじめの言い訳は、一切口にしないようにしてください。
言い訳しないと見せられないものは、載せないか、載せられるようにブラッシュアップします。
「仕事を頼もうかどうしようか」迷っている人を不安にさせるような態度をとらないようにしましょう。
注文が途切れないウェブデザイナーになる
注文が途切れないようにするには、まずは仕事をお願いしやすい人になっていく必要があります。
言い方は悪いですが、依頼する側にとって「感じのいい、便利な人」になることです。
「こういったこと、できますか」、「三日でできませんか」
と言われたときに「できます」
といえる体制を作っていくことです。
具体的には、次のことをやります。
小さい工夫を続ける
コーディングツールのショートカットを覚えたり、Emmetなどが使えるようになるとコーディングのスピードは格段に上がります。
PhtoShopは、アクション機能とバッチ機能が使えるようになれば作業スピードが上がります。
こういった工夫・改善はコツコツやるしかありません。
でも、やろうとしない人との差は明確です。
協力し合える体制を作る
一人の工夫ではどうにもならない時もあります。
頼れる人をたくさん作ることです。
僕はウェブの仕事を相談できそうな友人・知人がすぐに8人、頭に浮かびます。
信頼できる人に相談できる体制ができると、
「一人じゃ無理だけど二人ならできるかも」
「自分は今できないけど、他の人ならやってもらえるかも」
といったことも考えて仕事ができます。
こうした関係を持つことでも、仕事を途切れさせないようにすることが出来ます。
たとえフリーランスとして一人でやっていくにしても、長くやっていくためには、
たくさんのフリーランスとアメーバみたいにつながっていることが理想です。
単価を上げていくことをモチベーションにする
さて、「感じのいい、便利な人」を続けるのがしんどいという意見があります。
もちろん僕もそうです。
「感じのいい、便利な人」を続けるだけだと、ただのいいなりです。
そこはまだ通過点で、ウェブデザイナーはまだ目指すべき場所があります。
それは仕事の単価を2倍、3倍に上げていくことです。
単価を上げるために何をすればいいか。
方法は一つではないですが、「仕事をこなしつつ、単価を上げていく方法」について
私の方法をご紹介します。
単価を上げていく方法
注文が途切れないウェブデザイナーはになるのは、レベルでいうと優しいほうです。
言いなりになってめちゃくちゃ働けば、注文は途切れません。
滅私奉公的に仕事を山のようにこなしているウェブデザイナーさんをたくさん知っています。
でも、「めちゃくちゃ働いた結果、手元にはいくらも残らない」という状態を2年も3年も続けてはいけません。
単価の低い仕事は貢献感を得にくいです。単価の低い仕事を続けると、精神も枯れてしまいます。
もっと上のレベルを目指して、替えの利かない人になっていきましょう。
それは、オンリーワンのウェブデザイナーになるという事です。
替えの利かない人になることで、単価を上げられます。
では具体的に何をやっていけばいいでしょうか?
専門を絞ったサービスを持つ
専門というのは、分野でもいいし、技術でもいいです。
ただし、技術は勉強しやすい分、競争が激しく、賞味期限が短いのであまりお勧めしません。
たとえば「『React』と『Ant Design』が得意です」ということを専門にしようとしても、
そのフレームワークはどんどん仕様変更を続けるし、いつまでたってもハイレベルな勉強を続けなければいけません。
一番よくないのが、ウェブを知らない発注者にはまったく価値が伝わらないということです。
技術的な専門性よりもより分かりやすく単価を上げるのは、分野で専門的になることです。
たとえば、医療系のECに強いです。
建設業のウェブサイトに強いです。
といった分野です。
絞った分野でグロースハックもできる専門家としての立ち位置を作っていくことが出来れば、単価を今の2倍に上げるのは、思っている以上に簡単です。
先生ポジションを取る
今のウェブデザイナーのスキルはその辺で働いている人たちよりも比べられないくらいハイレベルな専門性と情報収集能力を持っていますが、それは業界のことを知らない人には伝わりません。
わからないから、「ウェブサイト5ページ5万円でお願いできますか?」
というめちゃくちゃなお願いをされるのです。
知らずにお願いするほうに罪はありません。
知らない人を教育する立場に回ることでも、単価を上げることになります。
人を教育するためには何かしか1位を取っておく必要があります。
すぐに1位が取れる方法があります。電子書籍を発行することです。
電子書籍を書く
先生ポジションを築く方法の一つは、まず、自分の専門分野で電子書籍を書きます。
文字量にして15000字を目指します。ひるむ必要はありません。
長めのブログの5記事分です。
ブログが書ける人なら書けます。
今お読みいただいているこのブログなら2.5記事分です。
Kindleへ本を出す費用は無料です。
それに、KindleならWordファイルで入稿できます。
Kindleで、誰も出していない切り口で本を出します。
たとえば「建設業の売上を上げるホームページ10個の工夫」とかで本を出すのです。
カバーの画像を作る必要がありますので、ご自身でデザインしてください。
この出版が売れるかどうかはあまり関係がないです。
しかし、内容はある程度実のあるものを書く必要があります。
この電子出版によって、まだ誰も本を出していないジャンルで1位になれます。
先生ポジションをとる
「出入り業者の一人」ではなく、先生としてのポジションを確立していくようにします。
先の電子書籍があるとやりやすいです。
電子書籍を出したうえで、発注者となる人を集めて講演(Zoomセミナー)をすると、先生ポジションを作りやすいです。
教えてくださいと言われる人になることができれば、単価は上がります。
また、他の方法もあります。
これはある程度トーク力が求められますが、
コンサルタント的な立場となり、結果を出すための良いデザインを教えられる人になるのです。
たとえば、デザイン案をケチって1案作るのではなく、3案作ります。
そのなかで発注者側に選んでもらういます。
発注者が3つのうち1つを選んだあとで「まだまだですね。今回の目的から考えると、そっちではなく、こっち(別の案)がベストです。
こっちが選べるようになると、デザインがわかってきたという事になるんですが。わかるようになるまで、一緒に頑張りましょう」
これが先生としての立ち位置トークです。
そんな失礼なことはないと思うかもしれません。
信じられないかもしれませんが、コンサルタントのトークは、この高さから話します。
決して、「出入り業者」ポジションにいきません。
腰が低い人もいますが、あくまでもそれはしゃべり方の話で、
「教えて差し上げます」というポジションがなければ、コンサルタントの関係は成立しないのです。
これをお読みになっているみなさんにもできるはずです。
いろんな業界を見ている僕にとって、ウェブデザイナーはムチャクチャ優秀な人の集まりだからです。
そして、ウェブはいまだなお、いろんな営業方法の中で、効果を一番上げる最強のツールであり続けています。
臆することはありません。
多くの社長は、お金を払った分だけ効果があると納得できれば、お金を払います。
ぜひこの位置まで目指してがんばってください。